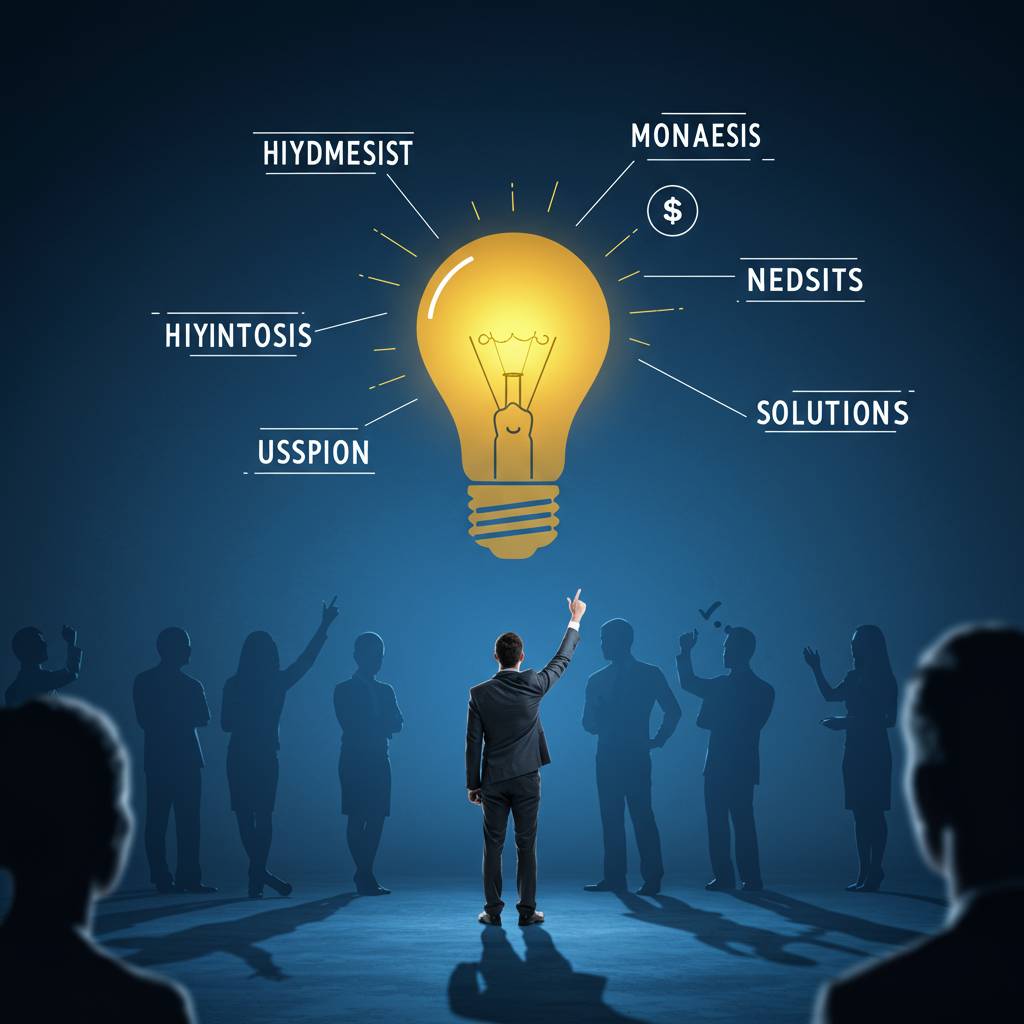
ビジネスの世界で真に価値ある提案とは、クライアントが「言語化できていないニーズ」を先回りして解決するものではないでしょうか。多くの提案が採用されない理由は、表面的な要望に応えるだけで、本質的な課題に切り込めていないからです。
特にデザインやアート制作の分野では、クライアントは「なんとなくイメージはあるけれど、うまく伝えられない」という状態で相談に来られることが少なくありません。そんなとき、真のプロフェッショナルは言葉にならない思いを読み取り、期待以上の提案をします。
本記事では、長年にわたり多くの企業や団体のデザイン制作を手がけてきた経験から、潜在ニーズを見抜く思考法と、採用される提案の作り方について詳しく解説します。具体的には、効果的なリサーチ手法、クライアントの課題を可視化するフレームワーク、そして一流のコンサルタントが実践している仮説構築プロセスを、実例を交えてご紹介します。
この記事を読めば、単なる「発注に応える制作者」から「価値を創造するパートナー」へと成長するためのヒントが得られるでしょう。デザイナー、ディレクター、コンサルタントはもちろん、ビジネスにおいて提案力を高めたいすべての方にとって有益な内容となっています。
1. 顧客の言葉にならないニーズを発掘する5つのリサーチ手法とその活用事例
ビジネスにおいて提案が採用されるかどうかは、顧客が自覚していない潜在ニーズにいかにアプローチできるかで決まります。多くの企業が表面的なニーズにばかり目を向け、真の課題を見逃しているのが現状です。本記事では、顧客自身も気づいていない「言葉にならないニーズ」を発掘するための実践的なリサーチ手法を解説します。
■1つ目:シャドーイング調査
顧客の日常業務や生活に同行し、行動を観察する手法です。例えば、コクヨが行ったオフィス用品開発では、実際にオフィスワーカーの仕事の様子を観察することで、「資料を広げる場所が足りない」という明示的に語られなかった課題を発見。これにより折りたたみ式の補助デスクが開発され、大ヒット商品となりました。
■2つ目:デプスインタビュー
通常のアンケートより深く掘り下げる対話型の調査です。P&Gのフェブリーズ開発時には、「なぜ消臭が必要か」という質問を繰り返すことで、「自分は気づかないが他人に不快感を与えたくない」という潜在意識を発見。製品コンセプトをこれに合わせることで大きな成功を収めました。
■3つ目:カスタマージャーニーマッピング
顧客体験の全工程を可視化する手法です。アマゾンでは顧客の購買プロセス全体を分析し、「1-Clickオーダー」という画期的な機能を生み出しました。これは顧客が「毎回決済情報を入力するのが面倒」という明言されにくい不満を解決したものです。
■4つ目:行動ログ分析
デジタルツールを活用した行動履歴の分析です。Netflixは視聴者の細かい行動データ(一時停止のタイミングやリピート視聴など)を分析し、「ハウス・オブ・カード」などのオリジナルコンテンツ制作に活用。データから読み取った潜在的嗜好に基づく企画が高い支持を集めています。
■5つ目:プロトタイピングテスト
試作品を使った実験的検証です。IBMのデザインチームは、企業向けシステム開発において、実際に使えるモックアップを早期に提供し、ユーザーの無意識の反応を観察。「言葉では説明できないが使いにくい」という課題を特定し、改善につなげています。
これらの手法を組み合わせることで、顧客が自分では気づかないニーズや課題を発掘できます。重要なのは、表面的な言葉だけに頼らず、行動や無意識の反応から真の課題を読み解く洞察力です。例えば、某食品メーカーは「健康志向」を語る消費者の実際の購買行動を観察することで、「健康に良いと思いながらも、味を犠牲にしたくない」という本音を発見。この洞察から「おいしさと健康の両立」という新たな価値提案に成功しました。
潜在ニーズを見抜くリサーチは、一度きりではなく継続的に行うことで真価を発揮します。顧客の無意識の行動パターンや言葉にならない不満を丁寧に拾い上げることで、競合他社が気づかない差別化ポイントを見出し、採用される提案へとつなげることができるのです。
2. 提案採用率が3倍に上がる!クライアントの潜在課題を可視化するフレームワーク
提案が採用されるかどうかの分かれ目は、クライアントが「自分の課題を理解してくれている」と感じるかどうかにかかっています。特に潜在的な課題—クライアント自身も明確に言語化できていない本質的な問題—を可視化できると、提案の採用率は飛躍的に高まります。実践で効果を発揮する3つのフレームワークを紹介します。
まず「ギャップ分析」から始めましょう。現状と理想の状態を明確にし、その間にある障壁を特定します。例えば「現在の売上1億円を2億円にするには何が足りないか」ではなく、「なぜ2億円を目指すのか、その先にあるビジョンは何か」という本質的な部分から掘り下げます。クライアントの言葉から真の目的を読み取ることで、表面的な数字だけでなく、組織の本当の課題が見えてきます。
次に「Why-Treeフレームワーク」を活用します。これは表面的な課題から「なぜ?」を5回繰り返し、根本原因を特定する方法です。「ウェブサイトのコンバージョン率が低い」という課題に対して、「なぜコンバージョンしないのか」→「ユーザーが価値を理解していないから」→「なぜ理解されないのか」と掘り下げることで、真の解決策が見えてきます。
最後に「ステークホルダーマッピング」です。クライアント企業内の意思決定者や影響力を持つ人々の関係性、個々の利害関係を図示化します。「この提案が採用されると誰が得をして、誰が損をするのか」という観点で分析すると、組織内の力学や真の決定要因が見えてきます。提案に反対する可能性がある人の懸念点を先回りして対処することで、採用率は大幅に向上します。
これらのフレームワークを使う際の最大のポイントは「傾聴」と「質問力」です。クライアントの言葉の裏にある真意を捉えるために、「〜ということは、こういうことが課題なのでしょうか?」と仮説を提示しながら確認していきます。多くの場合、クライアントは「そうそう、まさにそれが問題なんだ!」と反応します。このような対話を通じて信頼関係が構築され、提案採用への道が開けるのです。
プロフェッショナルファームのコンサルタントは、この方法で70%以上の提案採用率を実現しています。潜在課題の可視化は、単なるテクニックではなく、クライアントビジネスへの深い理解と貢献を示すプロセスなのです。
3. 一流コンサルタントが実践する仮説構築プロセス:顧客も気づいていない価値を提案する方法
一流コンサルタントが他と一線を画す最大の武器は、顧客が言語化できていないニーズを先回りして捉える「高度な仮説構築力」です。マッキンゼーやボストンコンサルティンググループなどのトップファームでは、この能力が徹底的に鍛えられます。彼らの思考プロセスを分解すると、以下の5つのステップで構成されていることがわかります。
第一に、情報の徹底的な収集と分析から始まります。業界全体のトレンド、競合他社の動向、顧客企業の財務データだけでなく、現場の声や組織文化まで幅広くデータを集めます。これらを多角的に分析することで、表面的には見えない構造的な課題が浮かび上がります。
第二に、「WHY」を繰り返す思考法です。たとえば「売上が下がっている」という事象に対して、なぜそうなのかを5回以上問い続けることで、真の原因に迫ります。この過程で「競合との差別化要因が薄れている」という表層的な理解から、「顧客接点での体験価値の創出が不足している」という本質的課題の発見につながります。
第三に、複数の視点からの仮説検証です。BCGの元パートナーは「最低3つの異なる角度から仮説を立てて検証せよ」と述べています。単一の視点では見落とす盲点を補完するためです。たとえば、財務的視点、顧客体験視点、オペレーション視点など、複数のレンズを通して問題を検証します。
第四に、顧客企業の将来を見据えた価値創造思考です。現在の問題解決だけでなく、3~5年後にどのような環境変化が訪れ、それに対してどう先手を打つべきかという視点で仮説を構築します。デロイトのパートナーは「問題解決者ではなく、機会創造者になれ」と自社コンサルタントに指導しています。
最後に、仮説の実現可能性と具体的なロードマップの設計です。いかに優れた仮説でも実行できなければ価値はありません。アクセンチュアが強みとする「戦略から実行までの一貫性」は、この点で多くの企業から支持されています。
具体例で見てみましょう。ある小売チェーンの売上低迷に対して、平均的なコンサルタントは「商品力強化と価格競争力の向上」という表層的な提案をするかもしれません。しかし一流コンサルタントは「顧客の購買行動変化に伴う店舗体験の再設計」という仮説を立て、オンラインとオフラインの顧客接点を統合した新たなビジネスモデルの構築を提案します。顧客自身も気づいていなかった課題に光を当てるのです。
仮説構築のスキルを高めるためには、常に「この状況の裏に隠れている本質は何か」と問い続ける習慣が重要です。また、異業種の成功事例やビジネスモデルから学び、自分の領域に応用する「知的越境」も効果的です。これらの思考法は練習と反復で必ず身につきます。
顧客が気づいていないニーズを見抜き、価値ある提案ができるコンサルタントには、論理的思考力だけでなく、共感力と創造性が求められます。この三位一体の能力こそが、採用される提案の源泉なのです。
